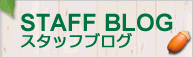第1回 金賞作品紹介

「ぼくたち、ふんばってるんだ」 鶴田 さくら

ぼくたちは、いろいろな場所にいる。
モコッとしていて、かたまっている。
そう、コケ。
森にいっぱいいるんだ。
木の根から、枝から、石ころから、
ウワァァァッて、生えている。
そんなぼくたちの、友だち。
葉瑠子ちゃんと、葉菜子ちゃん。5さい。
ソックリの双子で、
森のそばに住んでいるんだって。
風が教えてくれた。
二人は毎日森に来て、
ぼくたちの上でお昼寝してから、
木に登ったり、葉っぱを集めたりして遊ぶ。
たまに、キノコが生えていると、
それをつんでもって帰っている。
ほとんど食べられないキノコなんだけどね。
ものすごーくすべりやすい所だから、
二人がステン!と転んだ時、
ぼくたちはふんばって支えてあげる。
すると、
「葉瑠子、また転んだ〜。いつもゴメンね」って、あやまってくれるんだ。
だから、ぼくらはふんばって助けてあげるんだよ。
ある日、雨と風がすごく強くなった。
いつものおだやかな様子とは全然違う。
タイフウっていうらしい。
葉瑠子ちゃんたち、今日はここに来ない。
水を吸えるだけ吸う。土も手伝ってくれた。
すごい風。
ふんばっていないと飛ばされる。
あぁ、木が倒れちゃった・・・・・・。
でも大丈夫。人の家まではとどかない。
ふぅ、よかった。
葉瑠子ちゃんたち、あしたは来るといいな。
冬が来た。
毎日晴れているから、
葉瑠子ちゃんたちも毎日来る。
モコモコのダウンジャケットと、
厚手のジーンズで、着ぶくれいてる。
でも、どんなに寒くても、お昼寝は欠かさない。
ほっぺたをぼくたちにおしつけてねむる。
あったかいな。
夜。
森は静まりかえる。
キレイなしもばしらが立って、
キラキラ輝いている。
木も、氷のドレスをまとう。
ぼくたちも、氷でうすくコーティングされる。
寒いけど、ふんばってがまんする。
あしたも葉瑠子ちゃんと葉菜子ちゃんがくるから。
うーん、寒いなぁ。
あ、あれ?
ふわっ、ふわっと、
ワタアメを細かくちぎったような
かたまりがおちてくる。
ユキだ。
うわっ、まっしろになっちゃった。
寒さがましたような気がするけど、
これだけつもれば、二人とも喜ぶだろうな。
朝が来た。
木も地面も全部まっしろだ。
「葉菜子、まっしろだよぉ」
「雪ダルマつくろう」
エイエイとユキを転がして、
二人と同じくらいのユキダルマが完成。
まっかな顔をした二人は、ユキの上にたおれこんだ。
やっぱり、葉瑠子ちゃんも葉菜子ちゃんも大喜び。
ユキがふってよかった。
次の日には、もうユキはとけていた。
でも、ユキがとけたってことは、春が近づいてきた証拠。
あぁ、まちどおしいな。
やっと、春がきた!
からっと晴れているし、もういいかな。
それっ。
ぼくの子どものほう子(※)がまいあがる。
好きなところで、ふんばって生きろよぉ。
ぼくたちは、ふんばってるんだ。
※コケは種ではなく「ほう子」でふえる植物です。
雄株と雌株が出会ってできた「ほう子」が飛び散り、
地面などに落ちて発芽しコケに育ちます。

「森の守り主」 村田 尚紀
ある朝、ぼくはとつぜん目が覚めた。
ほのあたたかい何かに包まれたようなうす暗い場所から、
まぶしい光にあふれた、
ざわざわした音の中にほうり出された。
いきなりぼくというひとつの物体のスイッチが入ったかのようだった。
しばらくボウッとしていたぼくに、だれかが声をかけてきた。
蘚類スギゴケ科の一種である杉苔だった。
「おめでとう。初めての外のようすはどうだい?」
その言葉でようやく自分が何かの植物で、今さっき生えてきたことが分かった。
落ち着いてあたりを感じてみると、うす暗くじめじめしていて
おせじにも気持ちがいいものではなかった。
そのようすを上から見ていたカタクリが、むらさき色の花を
白鳥の頭のように下に向けてやさしく話しかけてきた。
「あなたが今いる場所は、じめじめして気持ち悪いかもしれないわね。
でも、そこでは私たちの栄養が作られているのよ。
あなたも栄養をいっぱい吸収して大きくなりなさい」。
こんな所にいても大きくなれるはずがないと、ぼくはまだふてくされていた。
しばらく時がたった。
いつのまにかぼくは、白鳥頭のカタクリと、黄色い可憐なシャガの花を
上から見おろすようになっていた。
それでもまだぼくより大きい仲間がたくさんぼくを見おろしていた。
そこでは、光沢のある赤い実をつけたアオキと、テングの葉ウチワとも呼ばれるほどの
大きな葉をもつヤツデがぼくをむかえてくれた。
「あなたがたは、もっと大きくなるのですか?」
今以上に大きくなったヤツデの葉とアオキの実を想像して、ぼくは楽しくなった。
「いや、わたしたちはもうこれ以上は大きくならないよ」。
ぼくは少しがっかりした。
そんなぼくを見て彼らは言った。
「きみはもっと大きくなるよ。
そして、わたしたちを見おろすくらい大きくなって、みんなの役に立つようになるよ」。
「役に立つって、だれの?」
「もちろん、森の仲間さ。
それに人間や動物のために、薬や食物になったりしてさ。
たとえば、ヤツデの葉は去痰薬(※)に、アオキの葉はやけどの薬として使われたりしているよ。
それから、虫や鳥、動物たちは、私たちの蜜や球根を食べて大きくなる。
そして彼らは、フンをしたり、花を咲かせる手伝いをして
わたしたちの成長を助けてくれているんだ。
それぞれがだれかの役に立っている。そうやって森は大きくなっているのさ」。
「人間は何をしてくれているの?」
「う~ん。それは大きくなってから、自分の目で確かめてごらん」。
※「去痰薬」とは、気管や気管支にたまった痰を吐き出しやすくさせる薬のこと。
月日が流れた。
ぼくは太陽をいっぱい浴びて、
針状の緑色の葉をしげらせて堂々と立つ杉の木になった。
ぼくの体はどんどん大きくなっていった。
すると、ぼくの枝にかくれている下の仲間が苦しそうにしだした。
「どうしたの?」
「きみが大きくなりすぎたせいで、下にいるわたしたちには、光や風が当たらないんだ。
このままだと窮屈で、大きくなれないよ」。
そう言われても、ぼくはどうしてあげることもできない。
ちょうどその時、木登りの装備をした人間たちがやってきた。
ぼくは切り倒されてしまうのではないかと、ビクビクしていた。
しばらくすると、人間がぼくの体をスルスルとのぼった。
のびきってボウボウになっていた枝や葉を、散髪でもするかのように下に落とし、
きれいにしていった。
散髪はとてもくすぐったいけど、気持ちがいい。
きれいになったぼくは、とても晴ればれした気分になった。
人間が切り落としたぼくの葉は、地面でまた栄養になる。
人間の作業が終わると、森はもとの静けさを取りもどした。
そんな中でぼくは考えた。
森を守っていくためには、森にいるすべてのものが必要なんだ。
そして、それぞれがその与えられた環境で生きていることが、
おたがいを支えていることにつながっているんだ。
人間はこの森にあるものを利用するかわりに、森の成長を助けていかなければならないんだ。
ちっぽけなぼくがここまで大きくなれたのは、
みんなが助けてくれたおかげなんだ。
そう思うと、感謝の気持ちでいっぱいになった。
それからぼくは、この森を守り、命のつながりの大切さを伝えていこうと、
背すじをピンとのばしてみた。
季節が何度もめぐり、いつしかぼくは森の守り主らしい大木になっていた。
木々の間をすりぬけるそよ風や太陽を浴びて、
きらめく葉たち、小鳥のさえずり、森のすべての生き物が
ぼくの成長を祝福してくれているようで、なんだかとてもくすぐったい感じがした。