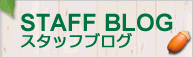KOBELCO森の童話大賞に関する、大きなこと小さなこと、色んな事を発信していきます。
2021.09.01 Wednesday
 9月に入りました!
9月に入りました!
こんにちは。
KOBELCO森の童話大賞事務局、みやです。
さて、今日から9月ですね!
今日から2学期の学校も多いのかな?
夏休みが終わると、童話大賞の応募も増えてきます。
今日9月1日に到着した作品たちはドーン!とこちらでーす!
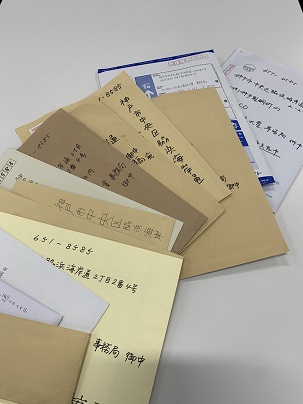
1つの小学校から30件の応募を頂きました。
また、第1回からずっとずっと応募してくださっている中学校から、今年もまた届きました。
こうやって先生方が学校でこんなのあるよ!と広めてくださる所から、
私たちの童話大賞は始まります。
先生、本当にありがとうございます。
もちろん、この封筒の中には、個人で応募してくださった方もたくさん入っています。
1人で2作品を書いて送ってきてくださった人もいました。
たくさんの枚数を書いてくださった人もいました。
具体的な植物の名前が色々登場しているお友達もいました。
このBlogを見たり、HPを見て、色々調べてくれたのかな?ととっても嬉しくなりました。
みなさん、本当に本当にありがとう!!
第9回の応募締め切りは9月7日(※消印有効)です!!
あと1週間!
最後まで、皆さんからのご応募、お待ちしております!!
2021.08.27 Friday
 KOBELCO森の童話大賞 書き方のヒント②
KOBELCO森の童話大賞 書き方のヒント②
こんにちは!
KOBELCO森の童話大賞事務局、みやです。
さて、今日は前々回にお話ししました「書き方のヒント」のその②です。
少し間が空いてしまったので、まずはその復習からしましょう。
KOBELCO森の童話大賞は「森」をテーマにしたおはなしを募集しています。
ストーリーは、みなさん子供ならではの発想力を思う存分発揮して、書いてね。
で・も、「森」を知って書くのと、知らないとでは大違い!
ということで、HPの「おはなしを書く前に」の「①森ってなぁに?」ページをご紹介しました。
そこでは、標高によって生えている木の種類が違う事をご紹介しました。
今日はその②ということで、それぞれの森の中についてご紹介をしていきましょう。
童話大賞のHPでは同じく「おはなしを書く前に」の「②どんな生き物が住んでいるのかな?」の部分です。
生えている大木、中低木、そしてそこに集まる動物や昆虫。
それぞれ生えている場所、種類によって、変わってくるんですって!!
例えば、ブナ林(夏緑樹林)の生物群集はこんな感じ。
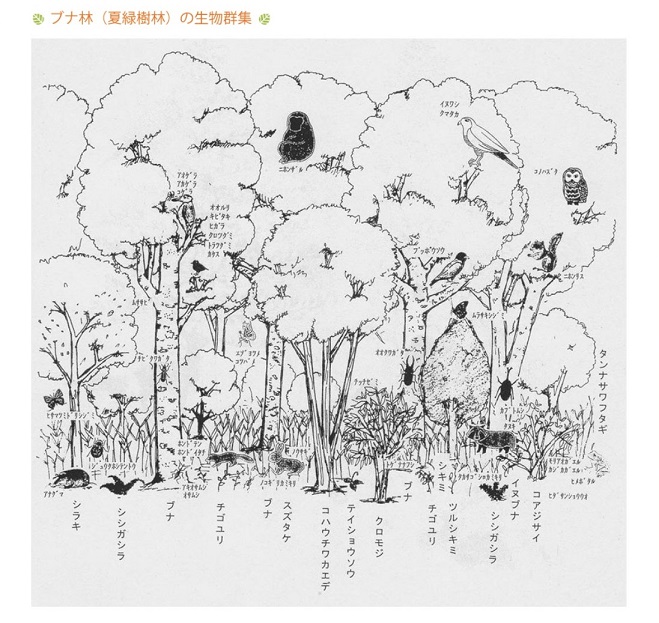
ブナ、シラキ、チゴユリ、クロモジ、コアジサイ…
高い木、中ぐらいの木、低い木、いっぱい植物の名前がありますね。
動物を見てみると、アナグマ、ノウサギ、ホンドテン、ホンドイタチ、ニホンザル、イヌワシ…
昆虫を見てみると、カブトムシ、オオクワガタ、ムラサキシジミ、モリアオガエル、ヒメボタル…
と、昆虫の場合、この図に出てくるすべてが一斉に無条件で登場するとは、限りません。
そう、季節が関係してきますよね。
もちろん、植物にも季節は関係してきます。
春に花が咲くものもあれば、夏に咲くものもある。
秋に実がなるものもありますね。
前回ご紹介しましたが、「夏緑樹林」ということは‥?
そう、夏は葉っぱが緑で、秋になると紅葉します!!
「森」ってとてもとても奥深い!!
一例としてブナ林でお伝えしましたが、
HPでは他にも
なども掲載しています。
さぁ!あなたはどこの森を舞台に、どの季節で、
何を登場させておはなしを書いてみますか??
ぼんやりと「森」を想像するよりも断然リアルなおはなしが書けるでしょう?
季節を決めたら、途端に色合い豊かなおはなしになりますね!!
そう、大事なポイントはそこでもあります。
絵本になることをイメージして、ぜひ、おはなしを書いてみてください。
金賞に選ばれたら、絵本作家のさとうめぐみさん、ながおかえつこさんが、
とっても素敵な絵本に仕上げてくれますよ!!
8月も最後になりましたが、
みなさんからの「森」をテーマにしたおはなし、
まだまだ待っています!!!
2021.08.17 Tuesday
 今年度初!の学校からの団体応募がありました!!
今年度初!の学校からの団体応募がありました!!
こんにちは。
KOBELCO森の童話大賞事務局、みやです。
さてさて!
お盆休み明けの昨日、今年度初!の学校からの応募がありました!!
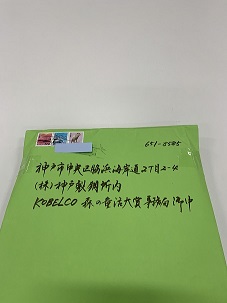
じゃ~~ん!!
先生が、HRのクラス課題としてご紹介してくださったようです。
将来、保育士や学校の先生などを目指すコースの高校生たち。
過去の絵本を色々読んで、
いつか子供たちに読み聞かせをするイメージも膨らませながら、
作品を書いてくださいました。
課題として取り上げてくださった、先生、本当にありがとうございました。
そして、絵本化をイメージして色々書いてくださったクラスのみんな、ありがとう!
さ、お盆が過ぎると、夏休みも終盤ですね!
夏休みの宿題・課題の中に、KOBELCO森の童話大賞はありましたか?
あった人はぜひ!
なかった人もぜひ!
金賞作品は絵本化される、「森」をテーマにしたKOBELCO森の童話大賞、
書いてみてくださいね!!
あなたからのご応募、お待ちしております!!