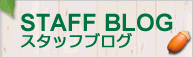KOBELCO森の童話大賞に関する、大きなこと小さなこと、色んな事を発信していきます。
2017.12.25 Monday
 永田萠さん、服部保さんと、台場クヌギを見てきました!!
永田萠さん、服部保さんと、台場クヌギを見てきました!!
こんにちは!
KOBELCO森の童話大賞事務局、みやです。
12月!!
今日はクリスマスですね!
さて、童話大賞では12月といえば、
永田萠さん、Rokoさんが、絵を描き始める頃です。
その前におさらいです。
審査会で金賞作品が決定すると、
永田萠さん、Rokoさんは、森の専門家の服部保さんと相談をして、絵本の舞台となる森を決めます。
そこには、どんな木が生えているのか、
どんな動物が住んでいるのか、
季節は…などなど。
そうして、資料を集め、絵を描いてくださいます。
前回ご紹介した、Rokoさんの「絵本ができるまで」の中の「その2」「その3」で、出てきますね。
と、もちろん資料だけではなく、
実際その森へ出かけることも、あるんです。
今回、永田萠さんと、服部保さんが、妙見の森に視察に行かれました。
今日はその日の様子を、ご紹介します!!!
今回、萠さんが描くのは、小学生の部金賞作品「クヌギの百年母さん」。
服部さんおすすめのクヌギがあるからと、集合したのは、
兵庫県川西市黒川の「妙見の森ケーブル 黒川駅」。
残念ながら紅葉の時期は既に終わっていて、
ケーブルも運行していませんでした。
その横の登山道を歩いて、さぁ出発!
森に入ると、立ち止まっては、木について、葉っぱについて、教えてくださる服部さんと、
写真に収めながら、お話を聞く萠さん。
そして、台場クヌギと呼ばれる、特徴的な形のクヌギの林に行きました。
1~3mの幹の途中で切っちゃうんです。
そうすると幹から枝が生え、それを10年ほどで、また切って・・・を繰り返していくと、
幹が太くなって、写真のような形になります。
(この写真にあるクヌギは100年ほど経っています)
切った枝は、焼いて炭にします。
ここの炭はとても有名なんですって!
菊炭(一庫炭)と言われるもので、
煙が出にくく、ばちっと火花が飛ぶ(爆ぜる)こともないそうで、主に茶道に使われるそうです。
林業遺産と、川西市の天然記念物にも認定されています。
と、他にも服部さんの解説は、続きます。
エドヒガン。
桜の種類で、ソメイヨシノより少し早いタイミングで花が咲きます。
幹に注目すると、縦に模様が入っていますが、これは成熟した木という事で、
幼い木は横に模様が入っているそうです。

ヤマコウバシ。
落葉樹なのですが、葉が落ちないことから、受験のお守りになるそうです。
このBlogを見てくれている受験生に皆さんに!!!!

山を下りて、こちらも服部さんおすすめのスポット。
この山。
右側には人の手が加わっていない自然林の照葉樹林。
昔からの神社があり、常緑の鎮守の森が広がっています。
そして、左側。
茶色くなっているのは紅葉している、落葉樹林。
人の手が入った里山林なんです。
落葉樹林は夏緑樹林とも言います。
夏緑樹林は林内が明るく、色々な植物が育ちます。
照葉樹林の林内は暗く、暗い所を好む植物しか生えていません。
自然林と里山林の両方がわかりやすく見えるこのスポットは、
学校の子供たちの見学でも立ち寄るようになっているそうです。
ナルホド。
※KOBELCO森の童話大賞のHPでも「おはなしを書く前に」というコーナーで、
森について、簡単に解説をしています。
ぜひとも見てみてくださいネ。
この日1日で、色んなことを学びました。
中々、森に行く機会なんてないですし、
しかも、森の専門家の方に色々解説してもらう機会なんて、本当滅多にないと思います。
だからこそ、みなさんも、そんな機会が巡ってきた時には、
ぜひとも森に行ってみて下さいね。
森を知る事。
それが私たちの目的「森を大切にする」ことの大切な第一歩なんですから。
さて、萠さんが取材した今回の妙見の森。
この取材を経て、どんな絵が出来上がるか、ますます楽しみになってきました!!

萠さん、よろしくお願いしまーす!!!!
2017.11.21 Tuesday
 Rokoさんの「絵本ができるまで(第4回)」のまとめ
Rokoさんの「絵本ができるまで(第4回)」のまとめ
こんにちは。
KOBELCO森の童話大賞事務局、みやです。
前回ご紹介した連載の「絵本ができるまで」が、見づらいなぁという事で、
今回、まとめのページを作成しました。
Rokoさんの「絵本ができるまで(第4回)」
見返すと、本当大変な作業ですよね。
こちらの絵本は、兵庫県内等後援自治体の小中高、特別支援学校、公立図書館に寄贈しています。
学校の図書室や図書館で「森のシャンデリア」を探して、
完成した絵本と、ラフの絵やボツの絵と見比べても面白いかも!!!
尚、現在も、第5回の絵本制作に取り掛かってくださっています。
永田萠さん、Rokoさん、今年もどうぞよろしくお願いします!!!
2017.11.17 Friday
 第5回KOBELCO森の童話大賞 審査会の様子
第5回KOBELCO森の童話大賞 審査会の様子
こんにちは。
KOBELCO森の童話大賞事務局、みやです。
先日、童話大賞のHPの方で、審査結果の発表を行いました。
もうご覧になられましたか?
さて、ここBlogでは、10月下旬に開催された審査会の様子をご紹介します。




審査員長の永田萠さん、審査員のRokoさん、服部保さん、
そして、今年度は文章の専門家というお立場でBL出版の落合直也さんにも審査に加わって頂きました。
みなさん、集まった様々な作品を前に、真剣に、時には笑顔を見せながら、意見を出し合い、審査をしていきます。
そして、小学生の部、中高生の部、それぞれの受賞作品が決定!!!

お疲れ様でした!の記念撮影ですが、審査員の皆さん、良い笑顔ですネ。
長時間の審査会でしたが、充実感でいっぱいです。
こうやって、審査された作品が、HPで発表された作品たちです。
受賞された皆さん、改めておめでとうございます!!!
さて、その中でも、金賞作品は、永田萠さん、Rokoさんの挿絵で絵本化されます。
これから、萠さん、Rokoさんの絵本制作がスタートします。
Blogでは、Rokoさんの「絵本ができるまで」を昨年度連載していました。
原稿用紙で応募された作品が、どうやって絵本になっていくのか。
「森」をテーマにしているKOBELCO森の童話大賞は、絵本化に関しても、妥協はありません!
舞台背景等々含めた裏話、絵本を作っていく順番、絵を描く事について、
Rokoさんが頑張ってくださった様子もあわせて、色んな情報が満載です。
みなさん、ぜひ見てみてくださいネ。
今年度も、どんな絵本が出来上がるか、わたしたちもとっても楽しみです!!!