どのように開発されたの?
KENIFINE™ 開発ストーリー
~菌・ウイルスが長生きできない世の中を目指して~

(1)開発のきっかけ 「O-157」食中毒事件
1996年7月に堺市で起きた「O-157」食中毒事件。抗菌材に対する注目度は高まりました。しかし、当時、銀や銅などを使用した抗菌材はあったものの、実使用条件では、抗菌性は認められませんでした。
そこに注目した当社は、私達の生活環境で抗菌性を発揮する本物の抗菌材の開発を開始し、ニッケル合金めっきに行き着きました。
ニッケル合金めっきは抗菌素材としての可能性を秘めている!
- めっきは当社の得意技術の一つ
- 各種部材に耐食性や耐摩耗性、意匠性などの機能を兼ね備える
- 工業的にも技術確立され、安価で大量生産が可能
- ニッケルは丈夫(高強度)で長持ち(化学的に安定)

ニッケルめっきに抗菌性を付与できれば、様々なものに適用できる
ニッケル自体は抗菌材ではありませんが、弱いながらも抗菌性を有しており、適正な組織・成分制御をすることで、その抗菌性能を極限レベルにまで引き出し、高めることに成功しました。
(2)一転、苦難の時代
開発目途が付き、技術の高さが世間に伝わるようになりました。各所から見積もりやめっき試作の依頼があり、量産を求める声があがってきました。
しかし、めっきの製造ラインの設備投資や人件費を入れると、めっき自体のコストが非常に高価になってしまい、その結果、商談につながりませんでした。
「めっきの製造ラインがなければ、いつまでたっても、試作・量産、ひいては、商談にならない・・・。」 苦難の日々が続きました。
めっきの試作・量産への壁
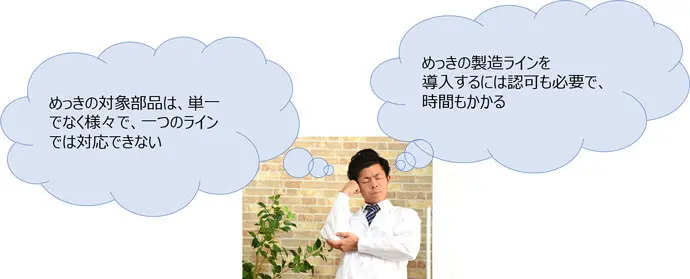
(3)方針転換 めっき会社に技術移転へ
悩んだ末に行きついたのは、めっき製造ラインを持つメーカへの技術移転でした。
メーカへの技術移転をすることにより・・・
- 既存のめっきラインが流用できる → 新たな設備投資が不要
- ロケーションも分散 → 輸送コストが下がる
- 各ライセンシーの持ち味・ノウハウスキルとケニファインが融合 → よりよい新製品作りが可能に!
- めっき専業メーカにおいても、新しいビジネスのネタ、競争力強化・生き残りにも繋がる

そう考えた当社は、抗菌素材の製造販売ビジネスから、めっき製造ラインを持つメーカに技術移転するライセンス事業に大方針を転換しました。
ライセンスを技術移転したメーカと連携して、ケニファインの利用技術(ケニファイン粉末など)の開発などを進めることになりました。
結果、20年以上の実績を積み上げ、現在では様々な用途に利用できるようになりました。









このように様々なものに利用できるようになったのは、当社が独占的に事業化せず、めっきノウハウやお客様のニーズに精通しためっき関連業者に広く技術供与する道を選んだことによる結果です。
今後も、当社はケニファイン技術を広く展開し、菌・ウイルスが長生きできない世の中を目指して貢献していきます。